最近読んだ2冊のタイトルの裏に教育の内容があって、非常に興味深かったので簡単に内容をシェアしようと思う。
 | 下り坂をそろそろと下る (講談社現代新書) 平田 オリザ 講談社 売り上げランキング : 967 Amazonで詳しく見る by AZlink |
本文中でマーキングしたのは次のような文章。
「いま社会から求められているのは、そこで感じた自然の素晴らしさを、色や形や音や、あるいは言葉にして他者に伝える能力である」
「日本社会にことに限って言えば、成熟社会、低成長型の社会へと社会構造を変えていく中で、複数のポジションを横断的に担えるような人材が強く求められるようになる」
「教員に、「ここからここまで試験に出るから覚えてこいよ」と言われ、それを従順に信じ、体力と根性で短期間に知識を詰め込む、そういった方面に能力のある人材は、しかし中国と東南アジアにあと10億人くらいいて、そこで国家としての競争力を保って行くには、もう無理がある。」
「本当に、本当に、大事なことは、たとえば平日の昼間に、どうしても観たい芝居やライブがあれば、職場に申し出て、いつでも気軽に休みがとれるようにすることだ」
「競争と排除の論理から抜け出し、寛容と包摂の社会へ。道のりは長く厳しいが、私はこれ以外に、この下り坂を、ゆっくりと下っていく方法はないと思う。」
教育に関して言うと、センター試験の将来的な廃止はニュースになって知っている方も多いかと思うが、大学受験が大きく変わろうとしていて、オリザさんもそこに関わっている。従来のようにただ知識や計算のスキルを問うだけでなく、与えられたテーマでディスカッションドラマ(討論劇)を創るだとか、紙芝居を創るだとか、創造性に加えて他者との役割分担、原初的な情報処理能力などが問われるようになっていくというのだ。
教育の現場は大きく変わろうとしていて、子どもたちには詰め込み型の勉強よりは本物の文化に触れて感性を磨いたり他者と交わったりする経験が重要になり、その変化を受け入れられる学校、自治体によって大きく差が出てくるだろうと氏は言う。また本物の文化に触れるには圧倒的に東京が有利なので、そこで地方格差が一層開くかもしれないという恐れもある。だが変化はもう止まらない。
これから義務教育を受ける子供を持つ身としては、グローバルな競争や人工知能が人間の知性を追い越す日(シンギュラリティ)が近いということも念頭に置きながら、このまま旧態然とした日本の教育を受けさせていいのかという疑問もあるなかで、日本の教育がどのように変わりつつあるのかを伺い知れたことは、非常にためになり考えさせられた。
 | 悩みどころと逃げどころ(小学館新書) ちきりん,梅原大吾 小学館 売り上げランキング : 155 Amazonで詳しく見る by AZlink |
タイプも考え方もまったくもって正反対のキャリアの二人が、足掛け4年、100時間にもわたって対談したのが本書の内容。第1章の「学歴」というテーマからして「学校って行く意味ある?」というちきりんに対して「大アリですよ!」というウメハラさん。事あるごとに意見が対立する二人だが、双方の思考がぶつかりあう様は格闘技のようにスリリング。ゲームの世界とは全く無縁のちきりんを注目させるに至ったウメハラさんの思考の強さ、深さがあちこちに立ち現われて唸らされる。
知らぬ間に私達を支配しようとする「学校的価値観」に対してのそれぞれのスタンスが面白い。共通しているのは、「どれだけ自分の頭で考えたのか」ということだろうか。学校キャリアにおいて両極端な二人の対談を読み進めることで、自分の歩みの相対的な位置を知ることにもなるし、子供の教育を考えるよい機会にもなると思う。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
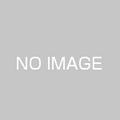



この記事へのコメントはありません。